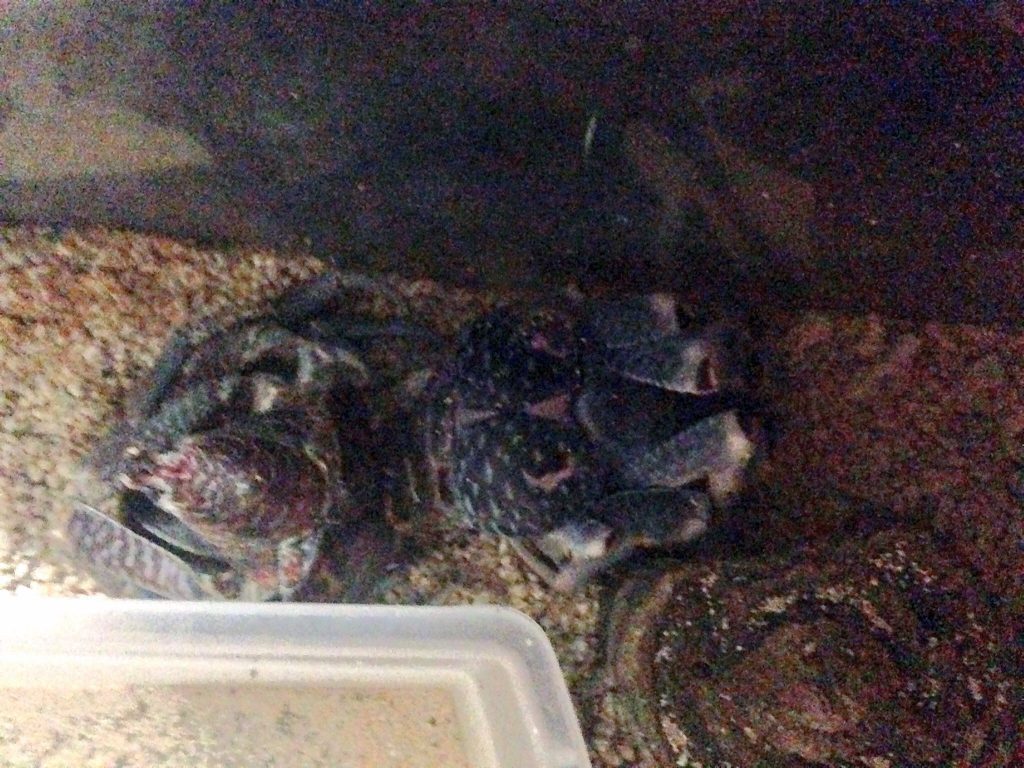ども、最近はクワガタの材割り採集にいそしんでおりますREPBUDDY ツルカワです。
たくさん採れた時は嬉しいです♪
さて、今日はカメレオンの餌について。。。
彼らは基本的に生きている昆虫や動いているものにしか興味を示しません。
慣れた個体であればピンセットや餌皿から乾燥コオロギや人工飼料なども食べますが、
食べる量や食いつきが違うそうです(絶食させてやっと食べるだとか。。。
そしてよくカメレオンの餌で言われるのが
「いろんな餌を与えないと餌に飽きて食べなくなる」「いろんな餌を与えると偏食してしまう」などなど・・・
そんな風に言われると余計にわからなくなりますよね?なので、今日は餌について書こうかと思います
※いまからお伝えするのはあくまで自論なので参考までに
餌に飽きるか飽きないかですが、人に慣れてピンセットから食べる個体であれば、たまに拒食することはあれど、
死ぬまでまったく食べないのはそうそういないかと思います。
偏食にしても一時的なもので、基本的には生きていて動いているもの、もしくはピンセットから食べる個体なら、
しばらく餌を抜けば、また食べるでしょう。
問題は、人に慣れていない個体やワイルド種などです。こういった個体が餌を食べない場合には、
様々な昆虫を見せて興味をそそるほかありません。
まず、基本的には主食はコオロギでかまわないと思います。
いま日本で一番入手しやすく、手軽でお手ごろ価格です。
与え方としては、栄養サプリをまぶしてから与えたり、野菜などをたっぷり与えてから餌にすると良いでしょう。
フタホシ派とイエコ派と分かれますが、私は管理の面からいうとイエコ派です。ただイエコだとボリュームに欠けるので大きく育った個体には
フタホシを与えていました。使っていた印象としては、フタホシは匂いが少しきついです。。。イエコはかなり素早いのでちょっとイラっとします←

こちらがヨーロッパイエコオロギ、黄土色でやわらかく動きが素早いです。
次に使いやすいのはミルワームやジャイアントミルワームですが、栄養はやや偏りがちで消化も良くないみたいです。私がエボシに与えた時も、
消化しきれずに形を残したまま排泄された時が何度かありました。しかしながら、食いつきはすごく良く動きも遅いので食べやすそうでした。
またジャイアントミルワームだとかなりの大きさになるので大きい個体にはオススメできるかもしれません。もちろんサプリメントを忘れずに。

こちらがジャイアントミルワーム、数が多いと鳥肌ものです・・・
同じワーム系だとシルクワームが有名ですね、栄養価が高く嗜好性もかなり高いのでカメレオンは喜んで食べるんですが、管理が難しいばかりか、
販売店も限られている、お財布には嬉しくないといった具合で、産卵前後や成長期にだけ与えるといった方も多いのでは?
近頃、我々の食用?でも有名な、デュビアも餌用生体としては人気ですね。コオロギより管理、繁殖が楽で栄養価も高く動きも遅めなので愛用者も多くなって
きました。それでも販売店が少なかったりするので、まだ普及しきれていないように思います。
採集してきた虫を与える方も多いですが、私はあまりオススメしていません。
カマキリやコオロギなど肉食や雑食の昆虫は寄生虫を持っていることが多いのです。
バッタにしても寄生虫の可能性が多少なりとあります。それに同じ大きさの昆虫を採集で常に用意できる人も少ないのではないでしょうか?
まだ比較的、採集して与えても良いといわれているのがセミです。
寄生虫の心配も少なく大きくばたつくので嗜好性が抜群です。特にカメレオンのワイルド個体や大型個体は喜んで食べるそうです。
私はそれでも寄生虫などが怖いので1度冷凍してから与えることをオススメしてます。。。
パンサーカメレオン食事シーン 与えているのはフタホシコオロギ
じゃあ、私は何を与えるかと言うと
メインはイエコを与えつつ、ジャイアントミルワームでボリューム、シルクワームで栄養を補おうと思います。
飼育希望種はジャクソンとパンサーなので、ジャクソンはイエコ、パンサーはフタホシになるかもしれませんが
次は具体的な飼育器具についてでも書こうかしら
See you again♪
みんなの相棒、REPBUDDYでした。
P.S.
最近では通販も売り切れることも少なくなってきたように思います。便利な通販もぜひご活用ください。下記リンクより通販ページへ↓↓
|
(生餌)ヨーロッパイエコオロギ M 80グラム(約280匹)北海道・九州・沖縄・航空便要保温 爬虫類 両生類 大型魚 餌 エサ
|
|
(生餌)フタホシコオロギ ML 40グラム(約80匹)北海道・九州・沖縄・航空便要保温 爬虫類 両生類 大型魚 餌 エサ
|
|
冷蔵★(生餌)ビッグミルワーム(ジャイアントミルワーム) 500g 別途クール手数料 常温商品同梱不可
|
|
(生餌)シルクワーム(カイコ) Sサイズ(50匹)
|